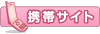公開日 2025年09月17日
消費者庁より情報提供
消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。
「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
※(注)「特別法人支援団体」、「生活復興支援窓口」、「NPO団体の支援機構」という公的に存在するかのような名称は、架空又は実在の機関とは関係のない機関名です。「厚労省」とかたる事業者と、国の行政機関である厚生労働省とは関係がありません。
トラブル防止のポイント
本件事業者は、「特別法人支援団体」といったあたかも公的に存在するかのような名称をかたる機関から消費者に支援金を給付するといったメールを消費者に送り、数千円から1万円程度の手数料を支払うなどすれば、多額の支援金が給付されるかのように告げていましたが、実際には、公的に存在するかのような名称は、架空又は実在の機関とは関係のない機関名が用いられたものであり、また支援金が給付されることはありませんでした(消費者を欺く行為)。
心当たりのないメールなどが届いた場合には、次のようなことに気をつけましょう。
・うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう。「支援金を受け取るにはまず〇〇円 を支払ってください」は典型的な詐欺の手口です。
・送金前に相談しましょう。送金してしまった後では取り戻すことは困難です。少しでも怪しいと感じたら、送金前に、一人で判断することなく、まずは家族や友人、同僚等に相談しましょう。
・まず冷静に相手の名前、会社名等をインターネットで検索することで、過去のトラブル事例や詐欺の報告が見つかることがあります。相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑うことも必要です。信頼できる相手かどうかを見極めることが、被害を未然に防ぐ第一歩です。
・知らない差出人からのメールや、心当たりのないメールには返信しない、メールに添付のURLにアクセスしないようにしましょう。添付のURLに安易にアクセスすると、偽サイト等に誘導され、個人情報や金銭をだまし取られる危険があるので無視をしましょう。
相談先
阿波市消費生活センター 電話:0883-30-2222
消費者ホットライン 電話:(局番なし)188
★消費生活センターでは副業に関するトラブルの他にも、消費者と事業者間のトラブル相談を受け付けています。
リンク
https://www.caa.go.jp/notice/entry/043484/(消費者庁ホームページ)
お問い合わせ
産業経済部 阿波市消費生活センター
TEL:0883-30-2222